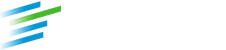基礎研究から運用までを自分たちの手で
そこから見えてくる新しい研究領域
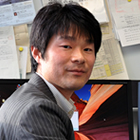
情報科学研究科 複合情報学専攻 複雑系工学講座 調和系工学研究室・准教授
博士(工学)川村 秀憲
プロフィール
1973年生まれ。94年北海道大学工学部、96年同大学大学院工学研究科修士課程、98年同博士課程修了。同助手を経て、2006年から現職。07〜08年ミシガン大学客員研究員、03年からNPO法人観光情報学会理事、11年から北海道観光振興機構情報システムWG座長。研究分野は人工知能、観光情報学、マルチエージェントシステム。主な著書に『マルチエージェントシステムの基礎と応用─複雑系工学の計算パラダイム』(共著,コロナ社、2002)、『生命複雑系からの計算パラダイム』(共著,森北出版株式会社、2003)。
社会問題を解決する実用的なサービスとしてのIT
調和系工学研究室ではどのような研究をしているのですか。
川村 調和系工学というのは、世界的にも例のない名称でしょう。人間社会にはさまざまな価値観が存在し、微妙なバランスのもとに社会が成り立っています。多様な意見・立場・利害が絡む社会的な問題は、一つの正解を提示すればすべてが解決するというものではありません。その中で、ITを活用してみんなが幸せになれるような落としどころを導き出すためにはどうすれば良いのか。単に便利なシステムを作るだけではなく、社会に深く根ざしたところで貢献できるITサービスを実現するにはどのようなアプローチが必要なのか。そういう観点でITを考えることが「調和系」という言葉に込められているのです。
もう一つ、私たちの研究室が重視していることは「論文を書いて終わりにしない」ということです。論文を発表し学界に貢献することは大切ですが、素晴らしい成果を上げても実社会で使われる機会に恵まれず、いわゆる「お蔵入り」で終わってしまうケースも少なくありません。研究成果を社会に適用するには泥臭い現場の問題にも立ち向かわなくてはなりませんが、自分のアイディアを実用可能なレベルまで作り込み、社会に役立つサービスとして提供できるという実例を示したい。そのため、2009年にベンチャー企業「調和技研」(解説1)を設立し、地域情報サイト「びも〜る」の運営を始めました。基礎的な研究から試作品の製作、運用までを自分たちで手がけることで、実社会のニーズをダイレクトに吸収し、それを研究にフィードバックしています。
ユーザの投稿を自動で選別・掲載する観光情報サイト
具体的にはどのような分野での活用を考えているのですか。

川村 北海道の大学であることを踏まえ、まずは北海道の基幹産業の一つである観光分野での適用を目指しました。道内の観光地では、自治体・民間を問わずさまざな事業者が観光情報の発信に力を入れていますが、今最も大きな問題となっているのが情報の更新です。ITに精通した人材も不足しており、せっかく開設したサイトも更新が滞るとユーザは離れていきます。そこで、私が参画している北海道観光振興機構の情報システムワーキングループが中心となり、まったく新しい方式による観光情報サイト「キュンちゃんねる」(解説2)を立ち上げました。
「キュンちゃんねる」の最大の特長は、ツイッターやフェイスブックなどのSNSを利用しているユーザが、「#キュン旅※※」(※※は地名やイベント名などを入れることができる)というタグを付けて投稿するだけで簡単に情報提供できることです。サイト運営者が情報更新する必要がなく、しかもリアルタイムな情報提供が可能になります。
現場に携わることで見えてくる新しい研究テーマ
サイトの構築・運営により得られた知見は今後どのように活かされるのでしょうか。

川村 「キュンちゃんねる」は、現代のIT社会における課題や要望に直接的に応えるものですが、その一方では私たちがこれまで気づかなかった新しい研究テーマを提供してくれました。その一つが、サイトを24時間動かし続けながらシステムのブラッシュアップを行う技術の開発です。例えば、掲載される情報の順番や重要度、画面の見やすさ、操作性などをコンピュータが自動的に判断し、デザインや機能を改良していくというもの。コンピュータがユーザの動向を常時解析し、自ら判断し、サービスを止めることなく最新・最善のものへ変えていく。動き続けるシステムの中で自律的に進化する技術の開発は、IT研究の中でも手つかずの領域でした。
また、「びも〜る」では、100万人規模の消費者実験やマーケティングリサーチを実現できないかと考えています。ある企業がサイト上で100万人のユーザに対して数種類のサンプルを提示し、人気のあるものを採用するといったものです。あるいは、ユーザデータを細かく分類し、ある特定のニーズを持ったユーザにだけ限定情報を流すための手法も研究しています。これらの実験は、他社のサイトを利用して行うことは難しいので、自前でサイトを持っていることは大きな強みになります。自分たちでサービスを提供しながら、ユーザや地域企業と対話を重ね、さまざまなテーマについて実験・検証を繰り返し、その成果を次のサービスに反映していく。そんな研究スタイルを築いていきたいと考えています。